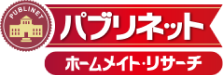都道府県庁情報(冬)
冬の都道府県庁情報/ホームメイト
都道府県庁の仕事は多岐にわたります。住民の生活を支える道路、上下水道、港湾などのインフラの整備や、公衆衛生、福祉、災害対策など、地域の住民を縁の下で支え住民の快適な生活を守る手伝いをしています。
年末年始から年度末に道路工事が増える理由
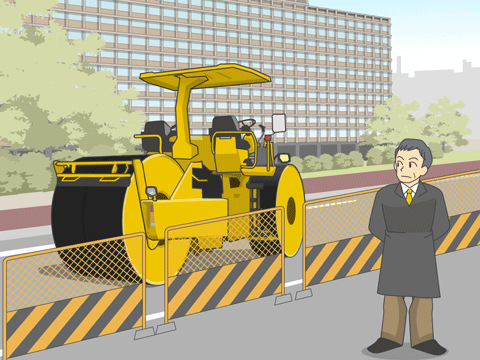
都道府県の土整備部と呼ばれる部署では、住民の生活を支える道路、上下水道、港湾などのインフラの整備・管理を担っています。他の行政機関などからの情報をもとにした工事案の作成、計画、工事業者の入札、実際に工事を行なう業者との折衝、工事の進捗管理なども行ないます。
道路には、高速自動車国道、国道、都道府県道、市町村道があり、国道には国が費用負担を行なう直轄国道と都府県が費用負担を行なう補助国道とがあります。この補助国道と都道府県道は、地域や都市内の主要な地点を結び、道路網の骨格をなす重要な道路で、都道府県庁が道路を管理。年末年始から年度末になると、街中で道路工事が増えているように感じることがありますが、実際には、道路工事は年度毎に計画されているので、毎年4月以降に工事が発注され、翌年3月の年度末までに工事を終わらせるようになっています。
特に車線数の多い幹線道路など主要な道路で工事が行なわれる場合には、大がかりな工事になることが多く、不便さを感じることでしょう。工事の進捗具合によっては、年度内に大急ぎで工事を終了させる必要が出てきたり、他工事とのスケジュール調整のために、工事の進捗を合わせる必要が出てきたりします。そのため、年末や年度末だけに道路工事が集中するように感じるのです。
冬に増える感染症への対策
空気が乾燥し、気温が下がる冬は、ウイルスが生存するのに最適な環境です。寒さのために換気がおろそかになり、冬場はインフルエンザやRSウイルスなどが広範囲で繁殖しやすくなります。また、人は体温が下がるとウイルスに対抗する免疫力が下がるため、冬場はインフルエンザやRSウイルスなどの感染症が急増します。
都道府県の福祉保健部では、感染症対策の部署を設け、感染症の発生に対し、対策の総合調整や感染症防止のための協力要請、物資の確保等によって、住民の生活、経済の安定を実施。また、インフルエンザなどの罹患者が増えたときなどには感染症情報を公開し、感染の拡大を防ぐとともに、感染者への適切な治療が施せるよう、医療機関等にも協力要請を行なっています。
各地にある都道府県営空港や港湾などでは感染症の水際対策として、飛行機等の利用者に対し、注意喚起を行なうと共に、サーモグラフィーによる体温の測定によって感染の可能性が疑われる人の聞き取りなどを実施します。
感染症の多くは、飛沫感染と接触感染、空気感染によってウイルスの感染が起こります。感染した場合には、医療機関への受診とともに、マスクを着用し、不必要な外出を控えるなど感染の拡大を防ぐよう心がけましょう。感染していない場合にも、ウイルスはどこに潜んでいるか分かりません。感染症注意報が出ている時期の外出時には、マスクを着用し、帰宅をしたらうがい、手洗いをすることでウイルスに感染しないよう心がけましょう。
冬季「大気汚染防止推進月間」の呼びかけ
冬季は、寒さのため家庭や事業所などで暖房機器を使用したり、交通量が増えたりし、大気環境が悪化します。また、窒素酸化物の濃度が高くなり、PM2.5が気象条件によっては発生。環境省では、毎年12月を「大気汚染防止推進月間」と位置付け、きれいな空を守ることの大切さを呼びかけています。
それを受け、各都道府県から大気汚染物質を減らすための取り組みを実施するよう、呼びかけがあります。個人レベルで取り組めることとしては、自転車や公共交通機関を利用したり、アイドリングストップなどエコドライブを実践したり、着衣を一枚多く着こんだり、暖房の設定温度を20℃に設定するウォームビズを取り入れたりする他、自動車の排ガスによる汚染を減らすエコカーへの買い換えなどです。きれいな空を守るため、できることから実践していきましょう。



都道府県庁では、住民と対話をしながら、快適な地域環境を作る取り組みや、地域の特色を生かした県政を行なっています。
防災とボランティアの日(1月17日)

1995年1月17日、阪神・淡路大震災が発生し、神戸地区を中心に大きな被害が出ました。町が崩壊し、多くの犠牲者を出したこの災害は、関西地区での戦後最大の自然災害として記録されています。この災害では学生を中心としたボランティア活動が活発化し、全国のボランティアが復旧に尽力しました。このときの教訓や精神を生かそうと制定されたのが「防災とボランティアの日」です。ボランティア活動への認識を深め、災害に備えた防災の強化を目的とし、この日を中心とした前後3日間を「防災とボランティア週間」と定めています。
この災害によって都市災害の問題点が浮き彫りになり、各都道府県では防災面の強化が図られています。特に、災害医療のあり方については、全国都道府県に災害拠点病院が設置されるようになり、災害時での救命体制の整備が進みました。
自然災害は避けることができませんが、被害が拡大しないように一人ひとりが心がければ、災害の規模を抑えることができます。万一の事態に備えて、災害対策をしておくとともに、防災意識を高めるようにしましょう。
県政世論調査
都道府県庁では、県民の意見や要望を聞いて、施策に反映していくために、毎年夏に「県政世論調査」を実施し、12月初旬に結果を公表しています。県内在住の20歳以上の男女を対象に、無作為で選んだ3,000~4,000人に対してアンケート形式で実施する方法で、住民の声を吸い上げます。調査項目については、県政についての満足度や各施策についての関心度をうかがうものから、都道府県ごとに進めようとしている事業やサービスに関するもの、生活環境など多岐にわたります。中には、東日本大震災後の復興状況や環境問題を調査した福島県であったり、米軍基地問題に対して意見を聞いた沖縄県のように、社会的に関心の高い内容を調査項目に盛り込む県もあり、その結果は県内だけでなく、全国からも大いに注目されます。
世論調査によって出た結果では、県政に対する県民の意識や関心度が分かるため、これをもとに、各都道府県では今後の事業推進、サービスの拡充・強化のための基礎資料とします。
地方公務員のボーナス
冬はボーナスが支給される季節で、一般企業へ勤めている人は楽しみにしているのではないでしょうか。都道府県庁に勤める職員たちも地方公務員としてボーナスが支給されますが、支給日や支給額は各都道府県の条例によって定められています。公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当の2つの手当を合算した額で、期末手当は定率で支給され、勤勉手当は勤務態度や実績に対する評価によって決められます。また、冬のボーナスの支給日は、国家公務員の場合は12月10日と法律で決められており、地方公務員もほぼこれに準じているケースが多いようです。
欧米などでは決算などの利益の配分で一時金が支給されることもありますが、基本的にボーナス制度がない場合が多く、ボーナスは日本独特の習慣です。その歴史は江戸時代にまで遡り、商人がお盆と年末に奉公人たちに配った仕着から来ているとされています。戦後の高度経済成長期には労働運動が活発になり、出費がかさむ夏と冬に、生活のための一時金が支給され、次第に会社の給与体系に組み込まれていきました。一般企業と違って実績に大きく左右されることがなく、安定した額が支給されますが、社会情勢を鑑みて民間企業に支給額を合わせたり、減額することもあります。
年の瀬を迎えると、都道府県庁では困窮者を励まし生活に困っている人たちが少しでも楽に新年が迎えられるように、様々な支援や協力を行なう「歳末たすけあい運動」が展開されます。また、その都道府県庁は、「仕事納め」と「仕事始め」の日が決められており、これは明治時代からの慣習で、現代まで長く続いています。
歳末助け合い運動
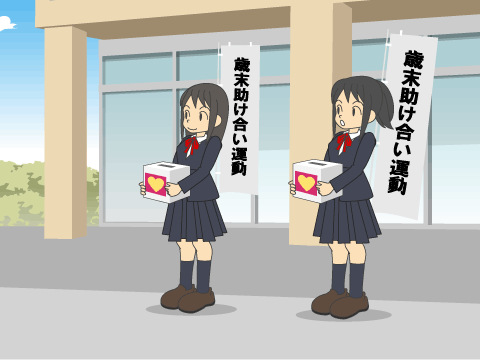
年末になると「歳末たすけあい運動」が展開されます。歳末たすけあい運動は、共同募金運動の一環として行なわれ、地域住民やボランティア、民生委員・児童委員の他、社会福祉施設や社会福祉協議会など、地域の関係機関や関連団体が協力して、支援を必要とする人たちが安心して新年を迎えられるように、募金をはじめとした様々な福祉活動を実施するものです。
この運動は、日露戦争が終結した翌年の1906年に、救世軍の山室軍平中将が「貧困と闘う家庭へ慰問袋を送り激励しよう」と呼びかけたことから始まったとされています。当時は、新聞の紙面で同情金の募集を読者に呼びかける程度でしたが、世界恐慌によって不景気となったことをきっかけに、全国で歳末同情週間が広まり、寄せられた寄付金で、貧困にあえぐ人たちなどに餅などが配られるようになりました。
さらに、第二次世界大戦で敗戦すると社会は混乱し、戦災者、引揚者、傷痍軍人(しょういぐんじん)、失業者など、助けが必要とする人が増えたことを受け、日本政府が「国民たすけあう運動」を提唱しました。この時に、共同募金を行なう「国民たすけあい共同募金運動」が開始し、また共同募金とは別に、同情品を募集する動きも各地で自然発生していきました。これが、「地域歳末たすけあい」の起源となっています。その後、年末に生活相談、就職斡旋、生活困難者への慰問・激励などの活動が行なわれるようになり、現在の「歳末たすけあい運動」へと発展しました。1959年には「歳末たすけあい運動」による募金と「共同募金」が一本化され、共同募金運動の一環として行なわれるようになりました。
高齢化社会や母子家庭など、現代は多くの社会問題を抱えており、募金の使い途、生活相談も多岐にわたっています。社会的弱者が地域で孤立することなく、新年を迎えられるように、できるだけ私たちも協力したいものです。
都道府県庁の「仕事納め」と「仕事始め」
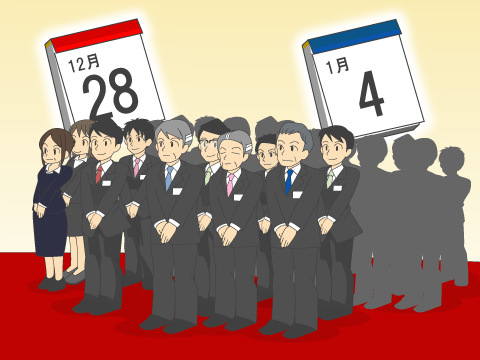
都道府県庁は毎年12月28日を「仕事納め」とし、1月4日を「仕事始め」としています。カレンダーによっては1~2日ずれることはありますが、ほとんど場合はこの日にちに準じています。都道府県庁だけでなく、ほとんどの官公庁がこの日に業務を終わらせ、仕事を始めています。「仕事納め」と「仕事始め」の日がそれぞれ決められたのは1873年で、この頃は「御用納め」や「御用始め」と言っていました。「御用」は本来、朝廷や幕府などの公用を意味する言葉で、役所の仕事は「お上の御用」という意味でした。これは、時代が明治に変わったものの、江戸時代の影響が残っていたからとされています。また、役人のことを「宮仕え」と言うこともありました。その後、「御用納め」や「御用始め」と言う言葉は長く使われ、1970年代までは一般的に使われていました。それが時代が変わるにつれて「御用納め」が「仕事納め」、「御用始め」が「仕事始め」へと変わりました。詳しい経緯は分かっていませんが、「御用」という言葉が時代にそぐわなくなったから、と言うのが有力な説のようです。ただし、カレンダーや手帳によっては、今でも「官庁ご用納め」、「御用始め」などと書かれているものもあります。