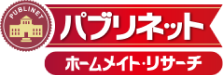官庁・省庁情報(冬)
冬の官庁・省庁情報/ホームメイト
国の土台である官庁・省庁が主体となって行なう取り組みやキャンペーンが多くあります。中でも冬には環境や文化、消費者意識を守るキャンペーンが実施され、国民の意識を高めるのに一役買っています。
環境に優しいウォームビズの取り組み

冬の地球温暖化対策として推進されている「ウォームビズ」。2005年(平成17年)に、秋・冬のクールビズとして提唱されたのが始まりで、環境省では、暖房の設定温度を20度で節電しながらも暖かく快適に過ごす工夫を行なう「ウォームビズ」の実施を、例年11月1日から翌3月31日までの期間を中心に呼びかけます。また、省エネ、低炭素型の製品やサービス、アクションなど、地球温暖化対策に関して、あらゆる賢い選択を推奨する「COOL CHOICE」という取り組みを関係省庁や様々な企業、自治体、団体等と連携して促進しています。
夏の節電よりも省エネ効果や二酸化炭素排出量の削減効果が高いと言われている冬の節電対策。自宅や職場、通勤手段、旅行などあらゆるライフシーンで、ウォームビズを取り入れる呼びかけをしています。デパートなどの人が多く集まる場所では、ウォームビズの効果は大きく、環境省は日本百貨店協会と連携し、冬の地球温暖化対策と家庭の節電対策を推進するため、暖房を消してデパートに集まることを呼びかける「ウォームシェア」も実施。衣食住にかかわる様々なイベントを開催し、快適に冬を過ごすアイディアも紹介されるので参考にするのも良いでしょう。
衣料品メーカー各社では、ウォームビズに関連する商品を毎シーズン販売し、ウォームビズの認知度の向上に貢献しています。
模倣品、海賊版撲滅キャンペーン
冬の寒い日は外に出かけるのを避け、家にこもってインターネットやDVDなどを鑑賞する人も増えます。近年インターネットの普及により増え続け、問題になっているのがブランド品の不法複製品やDVD、CDの海賊版。不法複製品や海賊版は違法なのはもちろん、購入する際に得た個人情報が悪用される可能性も高く、安いからといった理由で安易に入手しようとすることは非常に危険ですが、危機感がない若者が多いことも問題です。
特許庁では、こういった犯罪の撲滅を目指し、2003年(平成15年)度から「模倣品・海賊版撲滅キャンペーン」を実施。毎年12月から2月の期間、その年にあったテーマを決めキャンペーンを展開するもので、知的財産を守るため関係省庁と民間団体の協力を得てポスター、ウェブCM、特設ウェブサイトなどの広告媒体によって周知し、模倣品や海賊版を購入、容認しないという消費者への意識向上を訴求しています。消費者として、安易に模倣品を購入しないよう注意が必要です。
文化財防火デーに文化財愛護の意識を高める
1月26日は、文化財防火デーに制定されています。これは1949年(昭和24年)1月26日に、世界最古の現存木造建造物である法隆寺において、修理解体中の金堂で火災が発生し、壁画を焼損したことに起因します。この火災で、国民は大きな衝撃を受け、火災などの災害によって文化財保護の危機を憂慮する動きが生じ、翌1950年(昭和25年)には文化財保護法が制定されました。
1955年(昭和30年)に当時の文化財保護委員会(現文化庁)と国家消防本部(現消防庁)が1月26日を「文化財防火デー」に定め、文化財を火災や震災などの災害から守ること、全国的に文化財防火運動を広め、国民の文化財愛護に対する意識向上を目指しています。毎年、文化財防火デーとして、文化庁や消防庁、都道府県・自治体の教育委員会、消防署などが協力し、全国で文化財防火運動を実施。また、国宝を擁する各地の寺院などでも本格的な防火訓練が実施されています。



冬は官庁・省庁に関する記念日が多くあります。現代の私たちの生活に欠かせないものや、日本の国家を象徴するものが誕生した日を記念するもので、これらが現代日本を支えているとも言えます。
100円玉記念日(12月11日)

私たちが日頃使っている硬貨の中で、年間の発行枚数が一番多いのが100円硬貨です。 平成26年(2014年)の100円硬貨の発行枚数は約4億4,500万枚にものぼり、最もよく利用されている硬貨と言えます。その100円硬貨が誕生したのが1957年(昭和32年)12月11日で、この日を「100円玉記念日(または100円硬貨の日)」と呼ばれています。100円硬貨が登場するまでは100円紙幣が使われており、しばらくは併用されていましたが、今では100円の額面は硬貨しか発行されていません。
発行当時は、表に鳳凰、裏に旭日が描かれた銀貨でしたが、1959年(昭和34年)に鳳凰から稲穂にデザインが変わり、さらに1967年(昭和42年)になると、材質も銀から白銅に変更されました。現在のものは銅75%、ニッケル25%が配合され、直径22.6mm、重さ4.8gで、表にサクラの花、裏に100と製造年が入ったデザインになっています。
今では消費税の影響で、100円玉ワンコインだけで買えるものが少なくなりましたが、生活には欠かせない硬貨です。
天気図記念日(2月16日)
年末年始は、故郷への帰省や初詣、成人式など、イベントに出かけることも多く、お天気はやはり気になるところ。天気予報でよく示される天気図ですが、これは1883年(明治16年)2月16日に東京気象台が初めて天気図を作成した日とされています。ドイツの気象学者エリヴィン・クニッピングの指導で作られ、3月には印刷して毎日1回発行されました。
天気図は、高・低気圧が等圧線の形で書き込まれ、前線や台風の位置、風の向きなども示されます。気象庁では、「速報天気図」と「予想天気図」の2種類を発表しており、「速報天気図」は、午前3時から午後9時までの1日7回の観測データをもとに解析を行ない、観測時刻から約2時間10分経過したものです。
また、「予想天気図」は、午前9時と午後9時の観測をもとに、観測時刻から24時間後と48時間後の高気圧と低気圧の位置や前線、等圧線を予想したものです。これらの天気図をよくチェックして、年末年始の予定を立てましょう。
国旗制定記念日(2月27日)
1870年(明治3年)2月27日、明治政府は日の丸を国旗に制定し、国旗協会は、この日を「国旗制定記念日」に定めました。
明治時代に日の丸を国旗として制定したものの、実はそれ以前にすでに日の丸が使われており、701年の元旦に「日像の旗」が掲げられた記述が残っています。日像の旗とは、現在の横長ではなく縦長の形で、白い布地に赤い丸が描かれていたそうです。現存する最も古い日章旗は、1056年に御冷泉天皇から源頼義に贈られた日の丸の旗とされています。また、室町時代では勘合貿易で船に日章旗をつけていたことや、安土桃山時代に朱印船貿易の際に、日本の船籍であることを示すために船尾に日章旗が掲げられた記録が残っており、日章旗の発案自体は古い歴史があります。これは古来の太陽信仰によるもので、日本の国名そのものも「太陽が昇る国」を意味していることから、太陽を旗に描くことはごく自然な動機づけだったとされています。さらに、徳川家康や伊達政宗など多くの戦国武将も日章旗を好んで使っていました。
国旗国歌法の規定では、旗の形は縦が横の3分の2の長方形で、日の丸の直径は縦の5分の3の大きさで、丸の中心は旗の中心とすることが定められています。祝日に家の玄関先などに日の丸を掲げる風習は風化しつつありますが、最近はスポーツの国際試合などに日章旗を振ったり、フェイスペイントとして顔に日の丸を描くなどの光景が見られます。
「人権」は人であることで与えられる権利のことで、すべての人たちがその権利を主張することができます。毎年12月10日は「世界人権デー」となっており、「人権」について考えたり、世界的にいろいろなことが話し合われます。また、1月には皇居で「歌会始の儀」が開かれますが、国民も参加できる宮中行事として、話題を集めます。
世界人権デーと人権週間

私たちは生きていく上でいろいろな権利を持っています。これを「基本的人権」と言い、誰も侵すことができない権利です。1948年に国際連合の第3回総会において、すべての人間の自由と平等、労働の権利、教育を受ける権利、社会保障を受ける権利など、正義と平和の基礎である基本的人権を確保するため、すべての人民とすべての国が達成すべき共通の基準として、「世界人権宣言」を採択しました。2年後の1950年には、世界人権宣言が採択された12月10日を「世界人権デー」と制定し、国連加盟国、及び関係機関は、この日に人権活動推進のための活動を実施することを決議しました。
この宣言が採択されたことに伴って、日本では、法務省と全国人権擁護委員連合会が1949年から毎年12月4日~10日の1週間を「人権週間」と定め、各関係機関や関連団体が協力して、世界人権宣言の趣旨と人権の重要性を国民に広く訴えかけるとともに、人権尊重意識の高揚を図っています。期間中には、全国各地でシンポジウムや講演会、座談会、映画会などが開催され、テレビ・ラジオ・新聞など各種マスメディアを使った啓発活動を行なっています。
基本的人権には、「平等権」、「自由権」、「社会権」の3つの権利があります。「平等権」は、国が人を平等に扱うことで、人が国から差別を受けない権利です。「自由権」は、信教や思想、表現、居住、結社など、国によって干渉や介入ができない個人的な自由の権利です。「社会権」は、人が生活していくために国に配慮を求める権利で、生存権や教育を受ける権利、就労の権利などがあります。平等権と自由権は古くから世界で認められており、社会権は1919年にドイツのワイマール憲法で最初に定められたのを機に、多くの国が憲法で規定するようになりました。
歌会始の儀

新年を祝して、皇居では毎年「歌会始の儀」が開かれます。「歌会」とは、人々が集まって決められたお題で歌を詠み、その歌を披講する会のことで、奈良時代に貴族などの間ですでに行なわれていた宮中行事です。現在は皇室だけでなく、国民からも歌を募集しており、応募された歌の中から選出された選歌の作者は、皇居に招聘(しょうへい)されて、歌会始の儀に歌が披講(ひこう=詠み上げること)されます。この儀式は,読師(どくじ=司会役)、講師(こうじ=節をつけずに読む役)、発声(はっせい=第一句を節をつけて歌う役)、講頌(こうしょう=第二句以下を発声に合わせて歌う役)によって進行されます。なお、応募された歌は「詠進歌」、その作者は「詠進者」と呼ばれています。
歌会始の儀の進行は、天皇皇后両陛下の御前で、一般からの詠進歌、選者の歌、召人の歌、皇族殿下のお歌、皇后陛下の御歌(みうた)と続き,最後に天皇の御製(ぎょせい=お詠みになった歌)が披講されます。このときに、皇太子殿下をはじめ皇族方が列席され、文部科学大臣、日本芸術院会員、選歌を選ばれた詠進者などが陪聴(ばいちょう=身分の高い人と同席して聞くこと)します。
当初は、天皇がお催しになる歌会を「歌御会(うたごかい)」と言い、年の始めにお催しになる歌御会を「歌御会始(うたごかいはじめ)」と言いました。この起源は明らかではありませんが、鎌倉時代に宮中で歌御会が行なわれていた記録が残っており、それ以降、この「歌御会始」はほぼ毎年催されています。明治維新後も明治天皇により即位後最初の会が開かれ、1874年には一般の詠進が認められました。1879年には一般の詠進歌のうち特に優れたものを「選歌」とし、「歌御会始」で披講されるようになり、これまでの歴史の中で、宮中行事に国民が参加することは他に例がなく、画期的なものとされました。天皇の御製や選歌は「官報」にも掲載されるようになり、現在ではニュースや新聞でも取り上げられるようになりました。昭和になると、歌御会始が「歌会始」と言われるようになり、戦後には広く一般の詠進を募るために、「鳥」、「花」、「光」などお題が身近で簡単なものになりました。これにより、宮中行事だった「歌会始の儀」は国民行事へと移行し、現在では郵送だけでなくインターネットでも詠進歌を応募することができるようになっています。